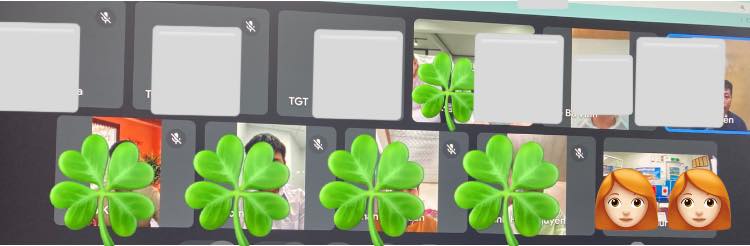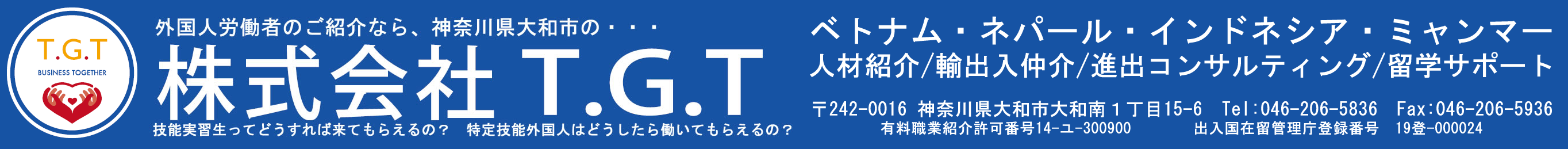特定技能概要
受入可能な16分野
1.介護、2.ビルクリーニング、
3.工業製品製造業(2-22年に3分野統合)、4.建設業、5.造船・舶用工業、6.自動車整備、7.航空、
8.宿泊、9.農業、10.漁業、11.飲食料品製造、
12.外食業、13.自動車運送業、14.鉄道、15.林業、16.木材産業
受入期間
- 特定技能1号は、最長5年(1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新)
- 特定技能2号は、更新(3年、1年又は6ヶ月ごと)可能で制限無
受入企業様の条件
- その業種を営む適切な免許や許可を取得している
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
- 受入機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制がある(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
- 出入国在留管理庁への各種届出
- 外国人への支援を適切に実施→支援については、登録支援機関に委託も可
特定技能外国人受入れに伴う支援業務
- 1号特定技能外国人支援計画
- 入国前の雇用契約内容確認等
- 飛行機など出入国のサポート
- アパート契約や銀行口座開設・携帯電話加入などの契約等のサポート
- 相談対応や生活面での入国後のサポート
- 日本語学習支援
- 定期面談実施や緊急時のサポート
- 日本人との交流支援等々
株式会社T.G.T 自動車整備経験人材教育
株式会社T.G.T特定技能運搬ドライバー教育紹介
よくあるご質問
-
特定技能に必要な書類は?
-
在留資格認定証明書交付申請時などには数多くの書類を提出します。詳しくはこちらをご参照ください。
-
特定技能の対象か仕事内容を確認するには?
-
日本産業分類で、まずは分野を特定します。且つ、技能実習制度の対象業務か確認してください。詳細については、担当者が丁寧にご説明させて頂きます。
-
人材を呼び寄せる費用や期間は?
-
受入機関(企業様)ごとの人数制限はありません。分野ごとに受入れ人数の目安は設けられております。
-
留学生アルバイトの在留資格を特定技能に変更したいのですが、対応可能ですか?
-
基本的には、卒業者が対象となります。また留学卒業生が特定技能への移行するには対象の試験への合格が必要となります。
-
配属時に通訳を依頼できますか?
-
可能です。幅広い分野の、言語の通訳対応が可能です。
-
外国人の生活サポートを依頼したいのですが。
-
アパートの契約や備品の準備の為に必要な情報から定期面談迄幅広く実施します。ご依頼される内容をまずはご相談ください。
-
配属前に生活ルールなどを教育してもらえますか?
-
神奈川県、愛知県と福岡県に常設の研修施設を完備しております。ゴミ捨てルールや自転車講習、警察講習など日本で生活するうえで必要な知識をしっかり教育いたします。
(ご要望に応じて、当社オプションサービスがあります)
特定技能制度とは
特定技能制度は、日本国内の深刻な人手不足に対応するため、2019年に創設された制度です。特定の産業分野で、一定の専門性・技能を有する外国人の就労を認める制度であり、産業の人材確保を主眼としています。
特定技能1号と特定技能2号の違い
| 区分 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 対象業務 | 相当程度の知識・経験が必要な業務 | 熟練した技能が必要な業務 |
| 在留期間 | 通算5年が上限(一度の許可は最長1年) | 上限なし(一度の許可は最長3年、更新可能) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 配偶者および子どもの帯同が可能 |
| 受け入れ分野 | 16分野(介護、外食業など) | 11分野(建設、造船・舶用工業など) |
受け入れ企業の条件
1.法令遵守 労働法や社会保険法を守り、賃金未払いなど不適切な行為を行わないこと。
2.適正な雇用契約 日本人と同等以上の報酬、福利厚生、労働時間を保証し、試験で証明された業務に従事させること。
3.支援体制の整備 住居確保、日本語学習支援、生活サポートなど、外国人が快適に働ける環境を提供すること。
4.非自発的離職の防止 労働環境を適切に管理し、契約終了後の帰国費用を負担すること。
5.帳簿管理 労働者情報を正確に記録し、必要に応じて提出できること。
6.欠格事由の防止 過去5年以内に重大な違反や犯罪歴がないこと。
7.文化の違いへの配慮 労働者の心理的ケアや、日本人との交流促進を行うこと。
特定技能1号における支援業務
受け入れ機関または登録支援機関には、以下の10項目が義務付けられています:
1.事前ガイダンスの実施
2.入国・帰国時の送迎
3.住居の確保や契約支援
4.生活オリエンテーションの実施
5.公的手続きへの同行
6.日本語学習の機会提供
7.相談・苦情対応
8.日本人との交流促進支援
9.転職支援(人員整理等の場合)
10.定期面談と行政機関への報告